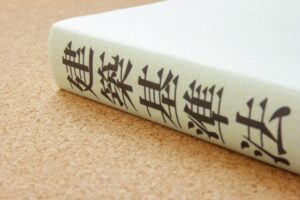屋根の下葺き材とは?種類別の特徴と選び方を徹底解説

屋根の下葺き材とは?その役割と重要性
屋根の下葺き材(したぶきざい)は、屋根材の下に敷かれる防水シートで、建物を雨や湿気から守る“第2の屋根”とも言える存在です。
主な役割は、屋根材の隙間から雨水が侵入した際に、その水を外へ排出し、建物内部への浸入を防ぐこと。これにより、構造材の腐食やカビの発生、断熱性能の低下などを防ぐことができます。
とくに近年の異常気象やゲリラ豪雨では、一次防水(屋根材)だけでは不十分なケースも増えており、下葺き材の性能がますます重要視されています。
しかし、下葺き材にも寿命があり、紫外線や熱による劣化、施工ミスなどが原因で十分な防水効果を発揮できないことも。だからこそ、素材の選定と正確な施工が不可欠です。
主な下葺き材の種類一覧
住宅の下葺き材にはいくつかの種類がありますが、現在の新築住宅では「改質アスファルトルーフィング(ゴムアス)」が最も一般的です。以下に代表的な4つの種類を紹介します。
1. 改質アスファルトルーフィング(=ゴムアス)
アスファルトにゴムや合成樹脂を加えて性能を強化した、現在の住宅における標準仕様の下葺き材。
現場では「改質アス」「ゴムアス」などと呼ばれますが、意味合いはほぼ同じです。
- 耐用年数:20〜30年
- 柔軟性・防水性に優れ、寒暖差や台風に強い
- 新築・リフォームを問わず幅広く採用
2. アスファルトルーフィング(JIS 1種)
従来から使われてきた安価な下葺き材。
価格は安いですが、耐久性に難があり、現在の標準仕様からは外れつつあります。
- 耐用年数:10〜15年
- 仮設住宅やコスト重視のリフォームで採用されることがある
- 長期性能を求める住宅には不向き
3. 合成繊維系ルーフィング(透湿・高耐久タイプ)
軽量で高耐久、かつ透湿性を持つ高性能シート。高気密・高断熱住宅に対応し、次世代の住宅性能にマッチしています。
- 耐用年数:30年以上の製品もあり
- 高性能住宅やZEH住宅におすすめ
- 製品によって性能差が大きいため、選定には注意
各下葺き材の特徴と用途
それぞれの素材には、使用に適した条件や建物の種類があります。ここでは実務現場の認識をもとに、違いをわかりやすく整理します。
改質アスファルトルーフィング(ゴムアス)
- 柔軟性・耐久性・防水性のバランスが良い
- 新築住宅では“標準仕様”として最も採用されている
- 呼び名の違いはあるが、実質的には同じと考えて問題ありません
アスファルトルーフィング
- コストが安いが、耐久性は短め
- 一時的な利用や予算重視の場面に限定される
- 長期的には再施工の手間とコストが懸念材料になる
合成繊維系ルーフィング
- 高い透湿性・耐久性で結露や劣化を防ぎやすい
- 高断熱・高気密住宅に適しており、性能住宅の定番になりつつある
- 価格が高く、施工者の経験が必要な場合もある
下葺き材選びの注意点と施工のポイント
いくら良い材料を使っても、施工ミスがあれば雨漏りや劣化の原因になります。
よくあるトラブル事例
- 屋根の勾配に合わない素材を使って雨水が滞留
- 釘の打ち方や重ね幅のミスで防水性が低下
- 素材の耐久年数を超えて使い続けてしまい雨漏り
選ぶときのチェックポイント
- 気候(台風、積雪など)に合った素材か?
- 下葺き材の耐久年数と屋根材の寿命が合っているか?
- メーカー保証や施工業者の実績があるか?
まとめ:屋根下葺き材は住宅性能の土台
屋根の下葺き材は、外からは見えませんが、家の寿命や安心感を大きく左右する重要な部分です。
現在は、「改質アスファルトルーフィング(ゴムアス)」がほぼ標準とされており、呼び名の違いで混乱しやすいですが、住宅の性能としては同等の扱いで問題ありません。
むしろ重要なのは、「どのグレードの製品が使われるのか?」「誰がどう施工するのか?」という点。
名称だけで判断せず、仕様書や施工図面、保証書での確認をおすすめします。
この記事を読んだ方へ
住宅の仕様説明や契約前の打ち合わせで、「下葺き材は何を使いますか?」と質問できるだけでも、後悔のない住まいづくりに一歩近づけます。
迷ったら、「改質アスファルトルーフィングで、耐用年数はどのくらいのグレードですか?」と聞いてみましょう。